発熱とは、体温が上昇し正常体温である37℃を超えた状態をいいます。発熱する時、さまざまな病気や状態が原因で起こります。例えば、新型コロナウィルス・風邪・インフルエンザなどの感染症は、発熱を伴うことがよくあります。
また、術後やケガをした傷口からの炎症など病気以外の原因で発熱することもあります。発熱した時は、なぜ発熱しているのかをまず特定することが大切です。そのため、まずは受診し医師に適切な診断を受け、症状にあった対応をしましょう。

内科系の症状

発熱とは、体温が上昇し正常体温である37℃を超えた状態をいいます。発熱する時、さまざまな病気や状態が原因で起こります。例えば、新型コロナウィルス・風邪・インフルエンザなどの感染症は、発熱を伴うことがよくあります。
また、術後やケガをした傷口からの炎症など病気以外の原因で発熱することもあります。発熱した時は、なぜ発熱しているのかをまず特定することが大切です。そのため、まずは受診し医師に適切な診断を受け、症状にあった対応をしましょう。
風邪、インフルエンザなどウイルス疾患、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎など細菌感染、その他の感染性微生物
膠原病、関節リウマチ、白血病など
外的要因で起きる体温調節機能の異常
ワクチン接種やアレルギー反応による一時的な発熱
特定の薬剤に対する副反応
月経、妊娠、更年期障害による体温調節機能の低下

咳と痰は、体内に侵入した異物から体を守るための大切な防御反応です。細菌やほこりなどの異物が気道に入ると、痰は異物をとらえるために分泌が増え、粘り気が強くなります。咳は、痰とともに異物を体外に出そうするために起こるのです。
疾患によっては、痰を伴わない乾いた咳のこともあります。
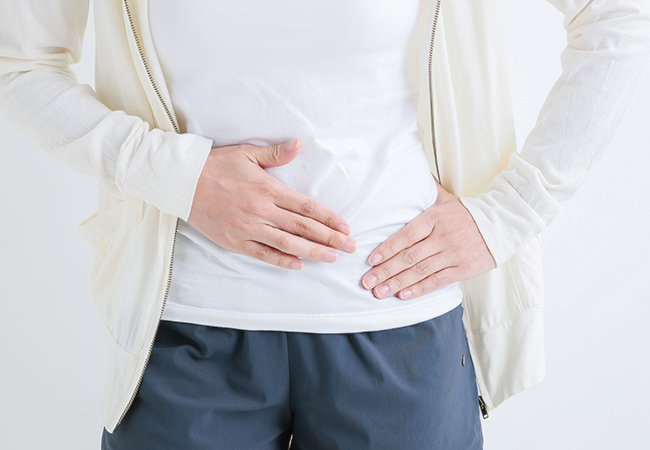
嘔吐(おうと)とは胃の内容物が口腔に逆流し、体の外へ排出される状態のことである。 嘔吐したくなる感覚を悪心または嘔気といいます。嘔気・嘔吐は何らかの原因によって延髄(えんずい)にある嘔吐中枢が刺激されて起こります。刺激が軽度であれば嘔気、それ以上であれば嘔吐といった症状が出現します。さまざまな原因が考えられるため、随伴症状から嘔吐の原因となる臓器系を絞り込むことが重要です。薬剤の副作用による嘔吐や女性では妊娠の影響も考えられます。緊急性が高い疾患が疑われる場合は、すぐに高次医療機関を受診しましょう。
下痢(げり)とは、24時間以内に3回以上、軟便または水様便が繰り返し排出されることです。症状の持続期間により急性、持続性、慢性の3つに分類されます。14日未満は急性下痢、14日以上30日未満を持続性(遷延性)下痢、30日以上持続する場合を慢性下痢と定義されます。
薬剤性下痢
感染性下痢
細菌性腸炎(サルモネラ、カンピロバクターなど)、ウイルス性腸炎(エンテロウイルス、ノロウイルス)など
炎症性腸疾患
虚血性腸炎、偽膜性腸炎
毒素(エンテロトキシン)による腸炎
コレラ菌や赤痢菌過敏性腸症候群、糖尿病など

不眠とは、「十分な時間が確保されているにもかかわらず、眠れない、あるいは眠りが浅いことで、日中の生活に支障をきたしている状態」を指します。

噯気(あいき)とは、げっぷのことである。胃に溜まったガスが、音を伴って食道・口腔を経て体外に排出される現象を指す。食べ過ぎや炭酸飲料を飲んで生理的に出ることもあるが、空気嚥下症や胃酸過多症によることもある。
胃もたれ、みぞおち付近の痛み、胃が膨らむような不快感とは胃に炎症が起きているときに起きやすい症状である。

頭痛(ずつう)とは、頭部の一部あるいは全体の痛みの総称である。
二次性頭痛
くも膜下出血・脳梗塞・脳出血・髄膜炎・脳炎・脳動脈解離・脳腫瘍など
一次性頭痛
片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛・薬剤性頭痛など
TOP